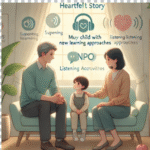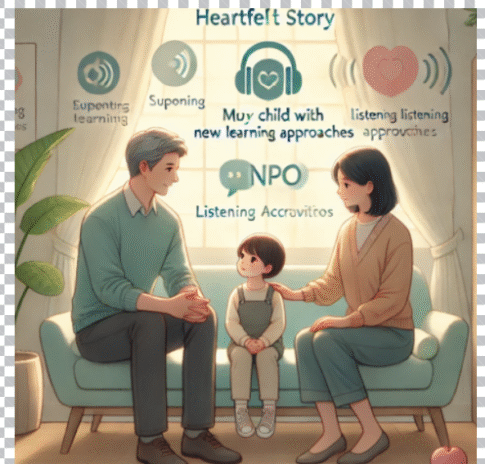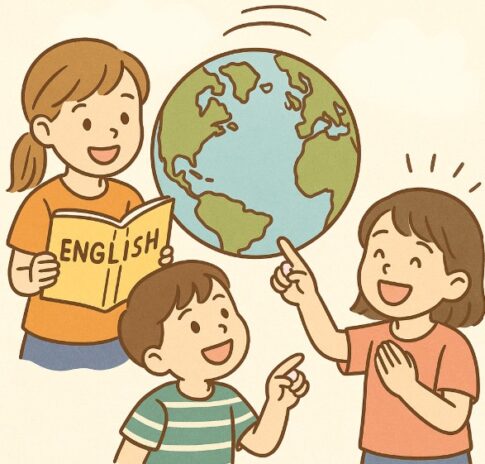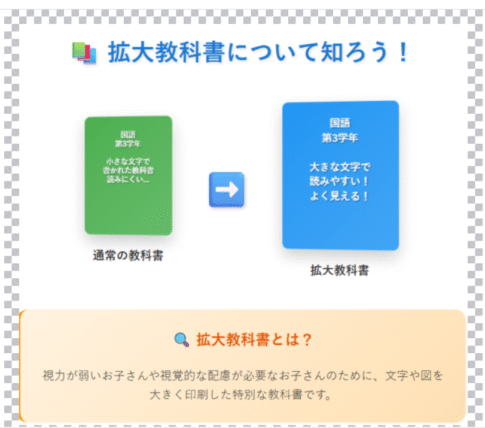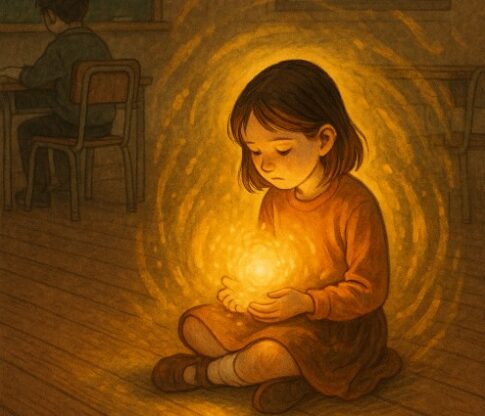――娘の合理的配慮をめぐって考えたこと
「学校が悪いのではなく、多くを求める世の中が学校を作っている」
ある人にそう言われて、ハッとしました。
娘の合理的配慮をめぐる葛藤
私は今、娘の合理的配慮について、学校と何度も話し合いを重ねています。
先生方は本当に一生懸命で、悪気なんてまったくありません。それでも、現実はいつも”平行線”のまま。
「やってあげたいけど、リソースがない」
「やってほしい、今必要なんです」
お互いが同じ方向を向いているのに、交わらないまま時間だけが過ぎていく——そんなもどかしさを感じています。
学校に悪意はない。でも、現場には”限界”がある
一つのクラスに30人程度の子どもたち。それぞれ違う背景や特性を持ちながら、限られた時間と人手の中で、先生たちは本当に頑張っておられます。
それでも、制度や時間、人的な制約の中で「やりたくてもできないこと」がたくさんあるのが現実です。
私は「それは理解している」と思いながらも、やはり”この子の今”に必要なサポートを願わずにはいられません。
私の娘にも学習障害の特性があります
娘は読むことや書くことに時間がかかります。でも、それは理解していないわけではなく、学び方のスタイルが違うだけ。少し支えがあれば、自分の力で考え、表現することができます。
学習障害は英語だけの問題ではなく、日本語の読み書き、記憶、思考の整理など、あらゆる学びに関わっています。少しの工夫と理解で、子どもの可能性は驚くほど広がります。
平行線の中で気づいたこと
学校は悪くない。でも、私だけではすべてを支えきれない。
「どうにかしてあげたい」私と、「できる範囲で支えたい」学校。どちらも間違っていない……
この”平行線”を通して感じたのは、教育の問題は、社会の価値観の問題でもあるということ。
「もっと早く」「もっとできるように」「もっと完璧に」
会社でも、同じ言葉をよく聞きます。「生産性を上げよう」「効率を上げよう」
社会全体が、スピードと結果を求める方向に進んでいます。そして、その価値観が子どもたちの世界にも入り込んでいます。
「早く覚える子が優秀」「すぐできる子がえらい」——そんな空気が、知らず知らずのうちに広がっている。
でも本当は、ゆっくり考える時間こそが、子どもの力を育てる。焦らず、自分のペースで進むことが、本当の意味での「学びの深さ」につながるのだと思います。
教育方針と現実のギャップ
日本の教育方針には「個性を大切にし、生きる力を育む」とあります。けれど現場では、同じペース、同じ内容、同じ方法が求められます。
“個性を尊重する”と言いながら、”同じであることを良しとする”現実。そこに大きな矛盾を感じます。
「個性を大切にする」とは、”違っていていい”を認めること。”できる・できない”ではなく、”どうすればその子が力を発揮できるか”を一緒に考えることが、本当の意味での「生きる力」だと思います。
世の中が変われば、学校が変わる
教育は、社会の鏡。”効率”や”結果”を求める大人の社会が変わらなければ、学校も、子どもたちの学び方も変わりません。
だからこそ私は、Colorful Portという小さな場所から、「比べない・焦らせない・その子のペースで学ぶ」という新しい価値観を届けていきたいと思っています。
どうしたらいいんだろう
正直に言えば、私もまだ答えを見つけられていません。
でも、娘の笑顔や生徒たちの”できた!”という瞬間を見るたびに、少しずつ未来が見える気がします。
「合理的配慮」とは、制度ではなく、”理解しようとする心”のこと。
社会が変われば、学校が変わる。そして、子どもたちの笑顔も変わっていく。
今日もまた、その一歩を考えながら——。